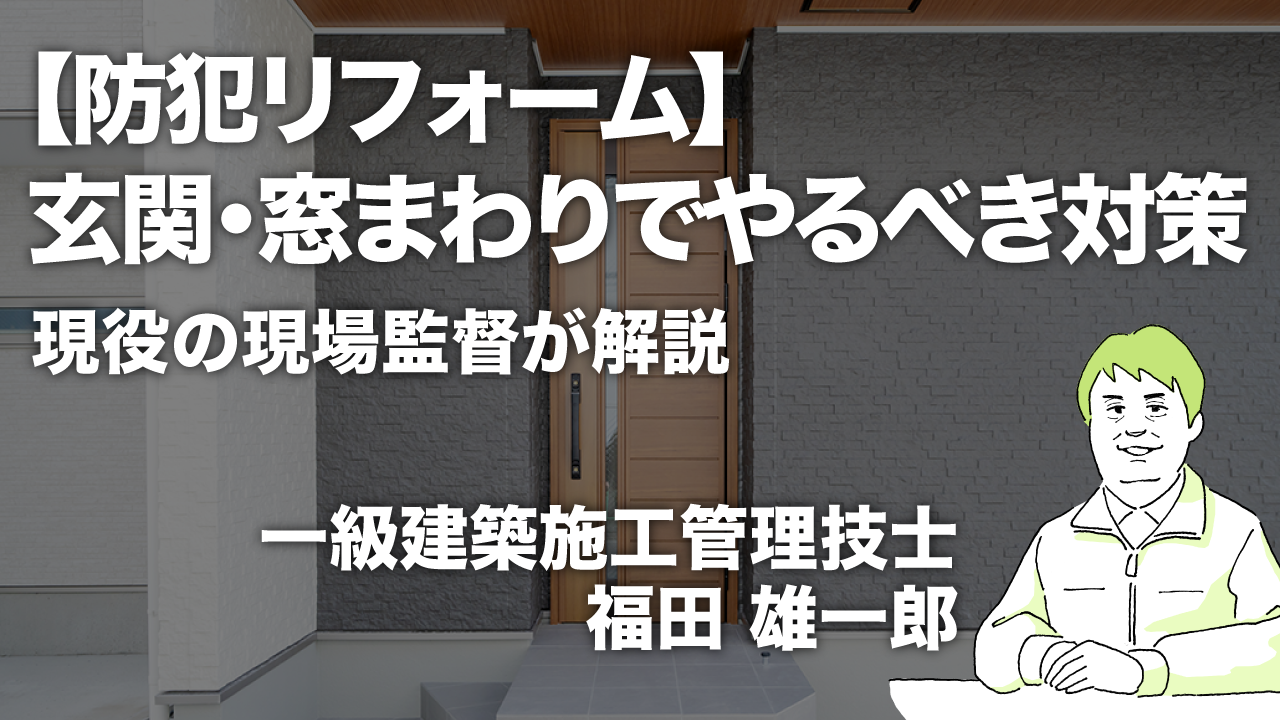秋から年末にかけては、暗くなる時間が早くなり、来客や荷物の受け取りも増える季節。実は、こうした“人の動きが多い時期”こそ、侵入犯にとっては様子を探りやすいタイミングでもあります。
本記事では、今の住まいを狙われにくく・入られにくく・被害を最小限に整えるために、玄関と窓まわりのリフォームでできることを順番に整理します。無料でできる基本から、少額で効く更新、さらに踏み込んだ強化策まで。読んだその日から実践できる内容に絞りました。
今回も本記事では、1級建築施工管理技士の現場監督・福田がポイントを詳しく解説します。
まずは施錠の徹底(無料でできる基本)

防犯の出発点はむずかしい設備ではありません。そんな当たり前のことと思われるかもしれませんが、「施錠の徹底」を“人の記憶”意識ではなく“家の仕組み”に落とし込むこと。外出が短時間でも、玄関と各窓を必ずロックする——これだけで、侵入の大部分は入り口で止まります。家族で“戸締まりの順番”を決め、帰宅後も窓は開けっ放しにしない時間帯を共有しておくがおすすめです。
二重ロックが使える窓は、日常運用に二重ロックを加えるだけで、侵入者に「ここは手間がかかる」と思わせられます。毎日の小さな積み重ねが、最終的にいちばん大きな抑止力になります。
現場監督 福田からのアドバイス①
「入られない家」を目指しすぎると費用が膨らみます。まずは「入るのに時間がかかる家」にする。
既に付いている補助錠を“標準運用”にするだけでも効果は大きいですよ。
玄関ドアは「鍵」と「ドア本体」をセットで考える

古いピンシリンダーのままなら、まずはディンプルキーへの交換が定番です。ピッキング耐性が上がり、合鍵管理もしやすくなります。合わせて、玄関ドア自体を二重錠・鍵穴が目立たない構造のタイプに更新できれば、そもそも狙われにくさが段違いです。
長期不在が多い、または小さなお子さま・高齢の方がいらっしゃるご家庭では、内側のつまみ(サムターン)が外せる脱着サムターンが役立ちます。ガラスを破って内側から解錠されるリスクを抑えられます。
現場監督 福田からのアドバイス②
“鍵だけ取り替える”より、ドア本体の防犯仕様も一緒に底上げしたほうが、結果的にコスパが良いケースが多いです。
玄関は“家の顔”。
見た目から“手強い家”にしておくのも大事な抑止になります。
窓は「ガラス・シャッター・錠前」で三層防御
 <当社施工事例>
<当社施工事例>
死角になりやすい面の掃き出し窓や引違い窓は、割られにくい防犯ガラスへの入れ替えが王道です。加えて、手動シャッターを最後まで降ろせば、実質的に“もう一つの鍵”が掛かった状態になります。
日常の閉め忘れが多い腰高窓には、閉めると自動で施錠される戸先錠付きのサッシが相性良し。操作の“ひと手間”を減らすと、毎日の防犯レベルが平均して上がるのがポイントです。
網戸は防犯目的の製品ではありませんが、外側から外しにくい納まりにしておくと、悪さをしようとする“最初の手がかり”をひとつ減らせます。
細い窓。その“幅”でリスクが変わる(026と036)
 <当社施工事例>
<当社施工事例>
「細い窓なら安心」——半分は正解ですが、実はサイズで差が出ます。
目安として、幅約36cm(いわゆる“036”)は“侵入しづらいが、条件次第では入れる”サイズ。幅約26cm(“026”)まで細くなると、そもそも侵入が現実的ではなくなると考えてください。 水まわりや通りから見えにくい面など、防犯優先の場所は026クラスを基準に検討すると安心感が違います。採光はやや控えめになりますが、安心>明るさの割り切りが必要な場所は確かに存在します。
現場監督 福田からのアドバイス③
お風呂・トイレ・脱衣室は、“のぞき”と“侵入”の両方の観点で「窓ゼロ」も選択肢。
どうしても付けたい場合は、026など侵入困難な寸法をおすすめします。
侵入犯が最も嫌う仕組みの導入(人感センサー照明・録画インターホン)
 <当社施工事例>
<当社施工事例>
侵入犯が最も嫌うのは、人に見られること。
玄関・アプローチ・駐車場には人感センサー照明を設置して、接近時にパッと点灯する仕組みを。
インターホンは録画機能付きに更新すると、不在時に押された呼び出しも記録でき、不審な訪問パターンの把握にも役立ちます。留守確認を装う来訪者への抑止にもなり、在宅時の“出る・出ない”の判断材料にもなります。
外構の防犯性を高める(見通しのいい外構+防犯砂利)
 <当社施工事例>
<当社施工事例>
高い塀や生垣に囲まれた家は、侵入後に隠れやすいという皮肉も。玄関〜庭にかけては、適度にオープンな見通しを作ると、そもそも近づきにくくなります。そういった観点からも山中木材では基本的にオープン外構を推奨しています。
また、建物の死角や勝手口の足元には、踏むと音が出る防犯砂利を敷くのも一手。
単体で劇的な効果を狙うより、照明・録画インターホン・砂利の三点セットで“気づかせる仕組み”を重ねるとバランスが良いです。
カメラ・ホームセキュリティ

ゼロ死角は現実的ではありません。だからこそ、屋外カメラで“見える化”を。
選ぶ際は、防水等級(IP65〜IP67)や夜間の可視距離、画角を確認してくださいね。
接続は安定性を重視して有線が基本。無線にするなら、通信環境と電源ルートの確保が前提です。
さらに踏み込むならホームセキュリティ。見守り+異常検知+ブザー+駆けつけを月額で外注するイメージです。侵入リスクが高い立地や、長期不在が多いご家庭では、心理的な安心も含めて費用対効果の高い投資になります。比較時は駆けつけ時間の目安もチェックしましょう。
長期不在は“在宅っぽさ”を演出——手軽なIoTの活用

旅行や帰省で家が空くときは、時間帯に合わせて照明をオン/オフできるスマートプラグ、タイマーで動くカーテンレールなど、無理なく扱える小さなIoTが役立ちます。
難しい設定は不要で、ポイントは「遠隔で動かせる」「外から見て“人がいる感”が出る」の2つ。屋内カメラは外から見えないように設置しつつ、ステッカーなどで“監視下”をさりげなく示すのも抑止になります。
費用と優先順位の考え方

防犯は“やるだけ全部”ではなく、段階的に積み上げるのがコツです。
まずは無料でできる基本(施錠の習慣化・二重ロックの常用)。
次に少額で効く更新(鍵の強化、センサー照明、録画インターホン)。
その上で、窓・ドアの本体強化(防犯ガラス、シャッター、戸先錠、ドア交換)。
最後に見える化と駆けつけ(カメラ、ホームセキュリティ)で仕上げる。 “使い切れていない装備を使う”“使いにくい装備は更新する”
——この順番なら、ムダなく確実に底上げできます。
よくある質問(FAQ)

Q1. 玄関は鍵交換とドア交換、どちらを先にやるべき?
A. 既存ドアの防犯仕様が弱い場合は、鍵だけで粘るよりドア+鍵をセットで底上げしたほうが、結果的に安心もコスパも高くなりがちです。まずはディンプルキー化で運用感を試し、必要に応じてドア本体を検討する流れが無理がありません。
Q2. シャッターは“防犯目的”でも効果がある?
A. あります。最後まで降ろせば、侵入までの時間が大きく延びるので、狙われにくさが増します。加えて台風時の備えにもなるため、大きな窓や死角側から優先して検討すると良いでしょう。
Q3. 細い縦すべり窓なら安心?
A. “細い”だけでは不十分で、幅の目安が大切です。036(約36cm)は“侵入しづらいが可能性は残る”、026(約26cm)は“侵入が現実的でない”——こう理解しておくと、場所ごとの適切な判断ができます。
Q4. 防犯カメラは無線でも大丈夫?
A. 無線でも使えますが、安定性と録画の確実性を重視するなら有線が基本。無線にする場合は、電波環境と電源の取り回しを先に確認してください。カメラ選定では防水等級・夜間の見え方・画角がチェックポイントです。
Q5. ホームセキュリティは“過剰投資”にならない?
A. 立地や不在の多さ次第ですが、見守り+検知+駆けつけを月額で外注できる価値は大きいです。心理的な安心も含め、“最後のひと押し”の仕上げとして検討するのが現実的です。
まとめ “狙わせない・入らせない・持ち去らせない”を重ねる
防犯リフォームは、生活の仕組みと設備の底上げを重ねていく作業です。 1つめは、閉めるを当たり前にする。 2つめは、玄関と窓を時間を稼ぐ装備へ。 3つめは、見える化と駆けつけで“最後の壁”をつくる。 この順番なら、家計に無理をかけず、毎日の暮らしも面倒になりません。
現場の実感としては、まず運用(習慣)を整えるだけでも、体感の安心は大きく変わります。そこに鍵・照明・録画インターホンを足し、必要な場所だけ窓・ドアの本体強化を。仕上げに記録と駆けつけをのせる。過不足のない“ちょうどいい防犯”がつくれます。
今日できるところから、ひとつずつ積み上げていきましょう。